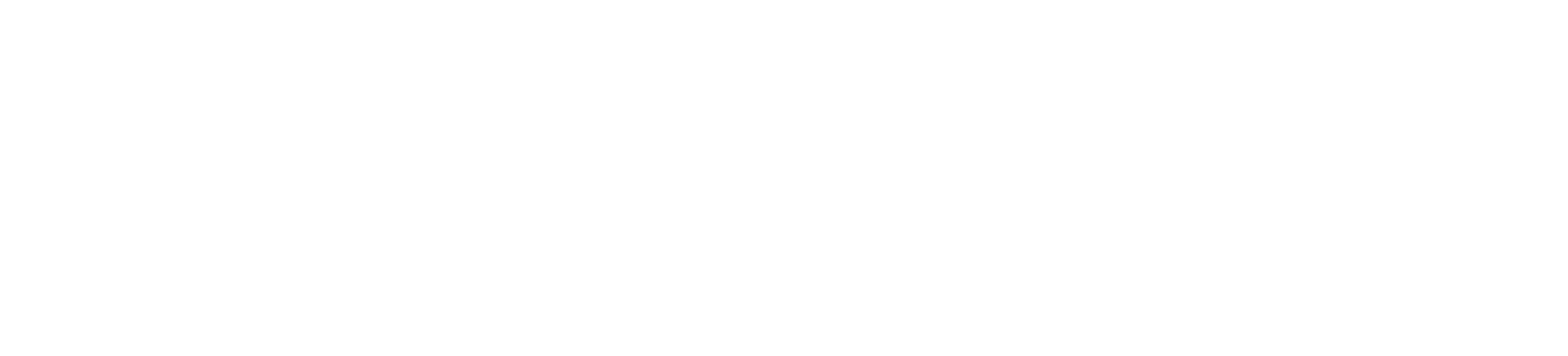私たちの体は、すべて脳や神経の働きによって動いています。立ち上がる、歩く、話す、考える、笑う――
これらすべては、脳が「指令塔」として全身をコントロールしてくれているからこそできること。
この「脳の働き」をより深く理解し、改善しようとするのが機能神経学(Functional Neurology)という分野です。
機能神経学とは?
「病気」ではなく「機能」に注目する神経学
一般的な医学では、「何かの異常があるかどうか(病気か健康か)」を診断することが中心です。
一方、機能神経学では、“異常があるかどうか”ではなく、“どう機能しているか”に注目します。
たとえば、「MRIでは異常がないけど、めまいや集中力の低下が続いている」といったケース。
こうした“原因不明”とされる症状も、脳の一部がバランスを崩している可能性があります。
脳の「再教育」によるアプローチ
機能神経学の面白い点は、脳を「再教育」することで機能を改善しようとするところです。
- 目の動きや姿勢のチェックを通して、どの脳のエリアが弱っているかを調べる
- 特定の感覚刺激(視覚、聴覚、体の動きなど)を使って、脳の活性化を促す
- 薬に頼らず、脳の「神経回路」を鍛え直すことで回復を目指す
これは、ちょうど筋トレのように「脳のトレーニング」をしているイメージです。
機能神経学が役立つかもしれない方
こんな症状にお悩みではありませんか?
- 慢性的な頭痛やめまい
- 注意力の低下・集中できない
- 首こり・肩こりがなかなか良くならない
- 原因がはっきりしない疲労やストレス
- お子さまの発達の偏り(落ち着きがない、学習の遅れなど)
もちろん、すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、
「どこも悪くないと言われたけど、つらい」という方には、新しい視点になるかもしれません。
おわりに
機能神経学は、まだ日本ではあまり知られていない分野かもしれません。
でも、「脳の働きに着目する」という考え方は、
私たちの体と心の健康に、新しい可能性をもたらしてくれます。
次回は、脳の「可塑性(かそせい)」というキーワードについてお話しします。
これは、年齢に関係なく脳が変わる力のことで、機能神経学の根本的な土台になります。